 |
平成20年度 神崎郡歴史民俗資料館講座録集 |
|
 ≪平成20年度連続講座≫ ≪平成20年度連続講座≫
平成20年度も、歴史民俗資料館で郷土の歴史や民俗行事について
学ぶ連続講座が全5回行われました。
本年は、「地域の歴史遺産を見つけよう」をテーマに、
各地で取り組まれている、歴史遺産の保全や活用事例、民俗行事について紹介いただきました。
また、第2回目の「水害で被災した史料の修復ワークショップ」では、
実際に史料レスキューについての講義を受け、参加者と一緒に歴史史料を守る方法を
学ぶことができました。
まずは、地域にある歴史遺産を身近に感じ取ることが、保全や活用へとつながるのでは
ないでしょうか。
来年度も、歴史民俗資料館では、さらに地域の歴史遺産について理解を深めていきたいと思います。
ぜひお気軽にご参加ください。
歴史民俗資料館で行われている、播磨地方における歴史や民俗行事についての連続講座です。
今年のテーマは「地域の歴史遺産を見つけよう」です。
「地域の歴史遺産を見つけよう」
~郷土への誘い~
| 開 催 日 |
講 座 名 |
講 師 |
場 所 |
時 間 |
| 第1回 |
5月24日(土) |
地域歴史遺産とは 済
-文化財の新しい見方を考える- |
奥村 弘氏
(神戸大学 文学部教授) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第2回 |
7月19日(土) |
水害で被災した史料の修復ワークショップ 済 |
河野未央氏
(尼崎地域研究史料館) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第3回 |
9月13日(土) |
柳田國男と民俗学-郷土を愛する- 済 |
佐々木泰彦氏
(関西国際大学 非常勤講師) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第4回 |
11月22日(土) |
地域の歴史遺産を活かしたまちづくり
-丹波市での事例を中心に- 済 |
松下正和氏
(神戸大学大学院人文学研究科
地域連携センター 研究員) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第5回 |
2月21日(土) |
火揚げ行事に見る伝承地区の技術とアトモスフェア
-姫路市朝日谷の事例から- 済 |
大渡敏仁氏
(芸術文化学博士) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
 平成20年度「地域の歴史遺産を見つけよう」講座録集 平成20年度「地域の歴史遺産を見つけよう」講座録集
<第5回 講座録>
日 時:平成21年2月21日(土) 13時30分~15時
演 題:火揚げ行事に見る伝承地区の技術とアトモスフェア-姫路市・朝日谷の事例から-
講 師:大渡敏仁氏(芸術文化学博士)
2月21日(土)、歴史民俗資料館で連続講座⑤が開催されました。
今回は、現在も姫路市・朝日谷地区で行われている「火揚げ行事」について
ご紹介いただきました。
講座では、現地調査等による詳細な映像やお話しから、
初めて知る行事であっても、理解を深めることができました。
竹で編んだ円錐形の籠に、初めて火のついた松明が投げ入れられた瞬間は、
思わず会場からも歓声があがりましたよ。
また、行事として執り行われているところの様子だけではなく、
その行事を支える地域の人々や準備する様子から、地域の活き活きした姿が
伝わってきました。
これは、当町においても共通するところがあり、
先人より伝えられてきた地域の歴史を守り伝えていく大切さを感じ取ることが
できたのではないでしょうか。
次年度も、歴史民俗資料館では、地域の方々と一緒に、
播磨地域の歴史や民俗行事について、学んでいきたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。
<第4回 講座録>
日 時:平成20年11月22日(土) 13時30分~15時
演 題:地域の歴史遺産を活かしたまちづくり-丹波市での事例を中心に-」
講 師:松下正和氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター研究員)
11月22日(土)、歴史民俗資料館で連続講座④が開催されました。
今回は、地域にある歴史遺産、文化財を活かしたまちづくりについてご講演いただきました。
「地域歴史遺産」は、今年の講座でも注目し、「地域歴史遺産」とは何か。
また、これらを守り伝えていくことがいかに大切であるか、ということを学びました。
第4回目の講座では、この「地域歴史遺産」を活用して、元気なまちづくり、地域づくりへと
結びつけた、実際の取り組みを丹波市の事例を中心にご紹介いただきました。
お話しのなかで、地域の歴史遺産には様々な活用方法があり、
地元にある資料を地元の方が中心となり、整理し、解読し、そしてまとめ、地域の方々にも
知ってもらうことや展示施設で資料を紹介する取り組みがありました。
一つの歴史資料をとおして、地元の方々が結びつき、そして理解を深めることが、
歴史を守り伝えていくことになり、元気な地域づくりになるということを実感できたのではないでしょうか。
また、いきなり地域歴史遺産を活用したまちづくりを考えるのではなく、
自分たちの住む地域にどんな歴史資料があるのか、そしてそれらの資料に理解を示し、
向き合うことが大切であるということを、会場でも共有できた時間でした。
地域の資料館としても、地域の方々との繋がりをとおして、
地域の方々の声を大切にしたいと思います。
<第3回 講座録>
日 時:平成20年9月13日(土) 13時30分~15時
演 題:柳田國男と民俗学-郷土を愛する-
講 師:佐々木泰彦氏(関西国際大学非常勤講師)
9月13日(土)、歴史民俗資料館で連続講座③が開催されました。
今回は、福崎町に大変ゆかりが深い柳田國男が登場です。
この待望のテーマについて、関西国際大学より佐々木泰彦先生にお越しいただきました。
柳田國男とその功績については広く知られ「民俗学の父」として称されています。
しかし一般的にはなかなか理解が難しいところもあり、少しでも柳田國男とその功績について
理解し親しみを持つことができないかということで、このテーマが実現しました。
当日は町民のみなさまをはじめ多くの方にご参加いただきました。
そして講座をとおして、民俗学が確立されていく歴史的な変遷や
民俗学という学問が実は私たちのくらしに大変密着したものであり、
一過性のものではなく、私たちのこの日常、行い、営みを守り伝えていくことの大切さや、
これらのメッセージを届けてくださった方は、他でもない柳田國男であるのではないかと
いうことを知り、「ふるさと」を想う気持ちを再認識することではないでしょうか。
このたびは貴重なお話しをいただきありがとうございました。
次回は、近年注目を浴びている地域の歴史遺産を活かしたまちづくりに
ついてご講演いただきます。ぜひまた講座でお会いしましょう。
<第2回 講座録>
日 時:平成20年7月19日(土) 13時30分~15時
演 題:水害で被災した史料の修復ワークショップ
講 師:河野未央氏(尼崎市立地域研究資料館/神戸大学文学部非常勤講師)
7月19日(土)、歴史民俗資料館で連続講座②が開催されました。
今回は、水害で被災した史料の修復について実演も交え、
河野未央先生にご講演いただきました。
災害時においての文化財に対する処置は、
早急に必要なものでありながら、人命の救助やライフラインの
確保が最優先となるため、遅滞するおそれが強いですが、
講演をとおして、そのような状況下でも「捨てない」ということが歴史を守ることであり、史料が修復できる
ということを学ぶことができました。
また実際に、修復作業へ備える史料への応急処置法をご指導いただけたことにより、
被災した史料をどのようにして処置するのかということを、参加者と一緒に理解を深めることが
できたのではないでしょうか。
自然災害により被災した史料を失うのではなく、先人より大切に伝えられてきた地域の歴史を守り、
未来へと紡ぐ大切さを実感した講座でした。
河野先生、そして参加してくださった皆さま。どうもありがとうございました。
次回は、いよいよ私たちの郷土を代表する國男さんのお話ですよ。
<第1回 講座録>
日 時:平成20年5月24日(土) 13時30分~15時
演 題:地域歴史遺産とは-文化財の新しい見方を考える-
講 師:奥村 弘氏(神戸大学 文学部教授)
今年も5月24日、歴史民俗資料館にて第1回目の連続講座がはじまりました。
今年は、「地域の歴史遺産を見つけよう」をテーマに、私たちの住む地域の文化財について
みなさんと一緒に考えます。
このテーマを考えるにあたり、今年は県内各地の市民・自治体と連携協力し、
地域の歴史遺産保全や活用について取り組んでおられる、神戸大学大学院地域連携センター
のみなさんにお世話になります。
第1回目は、センター長でもある奥村先生にお越しいただき、
「地域歴史遺産とは」何か、そして近年文化財を取りまく新たな環境から生まれてきている、
文化財活用の可能性などについてお話いただきました。
本講座へは地元の方々もたくさんお越しいただき、
お話をとおして、「地域歴史遺産」というものが私たちの身近なところにあるものであり、
それらに気づき、守り、伝えていくことの大切さを実感することができたのではないでしょうか。
次回は、水害により被災した文化財の修復方法について実践を交えて講義いただきます。
ぜひ講座へお越しいただき、修復方法を習得ください。
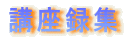
 平成19年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成19年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
 平成18年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成18年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
 平成17年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成17年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
◆問合せ先◆
神崎郡歴史民俗資料館
℡:0790-22-5699
※お問合せ・お申込みは資料館まで。 |
|
 |
|
|

